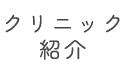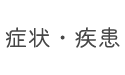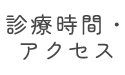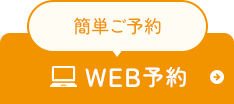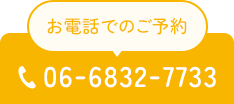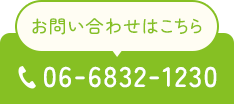小児ぜんそく(気管支喘息)は治る?重症度別の症状・原因・治療法をわかりやすく解説
「小児ぜん息」は、日常生活にも大きな影響を与える病気です。軽度の症状から重症化するケースまであり、正しい理解と早めの対応が大切です。本記事では、小児ぜん息の症状と重症度による違い、原因、治療法、そして気になる「治る可能性」についてもわかりやすく解説します。
- 小児ぜんそく(気管支喘息)とは
- 小児ぜんそく(気管支喘息)の症状
- 小児ぜんそく(気管支喘息)の重症度チェック
- 小児ぜんそく(気管支喘息)の発症のきっかけ(原因)
- 小児ぜんそく(気管支喘息)は治る?治療と予防について
小児ぜんそく(気管支喘息)とは
 喘息は、呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーといった音がする喘鳴を伴い、呼吸困難を引き起こす症状を繰り返す疾患です。気道の炎症や腫れにより、空気の通り道が狭まり、喘息発作が発生します。
喘息は、呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーといった音がする喘鳴を伴い、呼吸困難を引き起こす症状を繰り返す疾患です。気道の炎症や腫れにより、空気の通り道が狭まり、喘息発作が発生します。
子供の気道は成人に比べて狭いため、風邪などの感染症でも喘鳴が生じやすいです。喘息の症状は自然ないし治療によって改善、消失しますが、ごく稀に致死的となることもあるため油断は禁物です。
ヒューヒュー、ゼーゼーといった苦しそうな呼吸音や息苦しさが見られる場合は、気道の状態を速やかにチェックすることが大切です。何かご心配な点があれば、遠慮なくご相談いただければと思います。
小児ぜんそく(気管支喘息)の症状
喘息は色々な症状を示します。息が苦しい、呼吸時の喘鳴(ヒューヒュー、ゼーゼーという音)のほか、咳のみで表れる喘息もあります。
喘鳴がないからといって喘息でないとは限りません。次のような症状が続く場合は、医師の診察をお勧めします。
適切な治療を受けずに放置すると、気道の炎症が進行し、発作が頻繁に起こったり、症状が悪化したりする可能性があります。
- 風邪の後も咳が長引く
- 息苦しさや咳が続く
- 呼吸時にヒューヒュー、ゼーゼーという音がする
- 運動後に大笑いした際に咳や息苦しさを感じる
- 夜間や早朝に咳や息苦しさが増す
小児ぜんそく(気管支喘息)の重症度チェック
 喘息の症状の程度と発生頻度を基にして、その重症度を判断します。
喘息の症状の程度と発生頻度を基にして、その重症度を判断します。
重症度は「間欠型」「軽症持続型」「中等症持続型」「重症持続型」の4つの段階に分けられています。
間欠型(症状から判断した重症度)
年に数回、季節によって咳や軽い喘鳴が発生することがあります。時には呼吸困難を感じることもありますが、β2刺激薬を使用すると、症状は比較的速やかに改善します。
軽症持続型(症状から判断した重症度)
月に1回以上、もしくは週に1回未満で咳や軽い喘鳴が発生することがあります。時折、呼吸困難を感じることもありますが、これは持続せず、日常生活には大きな影響を与えないと考えられています。
中等症持続型(症状から判断した重症度)
週に1回以上、咳や軽い喘鳴が発生することがありますが、毎日は続かない状態です。中程度から重度の発作(注)を引き起こす可能性があり、日常活動や睡眠に影響を与えることもあります。
重症持続型(症状から判断した重症度)
毎日咳や喘鳴が起こり、週に1~2回は中発作・大発作(注)が発生する状況です。
これにより、日常生活や睡眠にも支障をきたします。
小児ぜんそく(気管支喘息)の発症のきっかけ(原因)
 小児喘息の病型分類として、アトピー型と非アトピー型があります。
小児喘息の病型分類として、アトピー型と非アトピー型があります。
アトピー型とは吸入アレルゲン(花粉やイヌ・ネコの毛、ハウスダスト、ダニなど)に対する特異的IgE抗体を証明しうるもので、非アトピー型はそれを証明できないもの(ヒトライノウイルスやエンテロウイルスなどのウイルス感染、たばこの煙、PM2.5、黄砂など)です。
小児喘息の患者さんの多くはアトピー型で、特にダニアレルギーが多いです。ホコリの多い環境での咳や喘鳴は、ダニを含むハウスダストへのアレルギー反応が原因である可能性が高いです。しかし、喘息の引き金となる要因は多岐にわたり、アレルゲンのみならず運動によっても喘息発作が引き起こされることがあります。
お子さんがどのような状況で喘息発作を起こすかを理解し、その誘因を把握することで、増悪リスクを減らすための適切な対策を講じることが可能です。
アレルギー
アレルゲンとは、アレルギー反応を引き起こす物質のことです。その種類は非常に多いですが、主な吸入アレルゲンは血液検査によって容易に特定できます。ハウスダスト、ダニ、ペットの毛やフケ、カビなどの環境アレルゲンが喘息発作の原因となる場合、適切な環境整備によって喘息の急性増悪(発作)を予防することが可能です。
ウイルス
ウイルス感染症は喘息の発症と増悪の双方に関連していると言われています。
発症に関わるウイルス
RSウイルス
乳幼児期に気道感染症を起こすことが知られており、1歳までに約70%のお子さん、2歳までにほぼすべてのお子さんが感染すると言われています。RSウイルスの多くは上気道炎で終わりますが、一部の乳幼児で下気道感染まで進行し喘鳴・呼吸困難といった喘息類似の症状を呈する細気管支炎を発症します。
特に重症のRSウイルス細気管支炎においては、罹患後に半数以上の児で気道過敏性の亢進が持続し喘鳴を繰り返すだけでなく、その後も喘鳴、喘息、アレルゲン感作の危険因子になると報告されています。
ヒトライノウイルス
ヒトライノウイルスは数百種類の血清型を持つため、繰り返し感染します。以前は上気道炎の原因ウイルスとされていましたが、乳幼児の細気管支炎の原因にもなり、小児喘息の発症や増悪にも関わることが、近年明らかとなってきました。
ヒトメタニューモウイルス
乳幼児期の気道感染症を起こすウイルスで、RSウイルスと同様に乳幼児期早期の細気管支炎や喘鳴の原因となります。2歳までのヒトメタニューモウイルスの感染がRSウイルス細気管支炎に罹患するより、喘息発症の危険因子になると報告されています。
増悪に関わるウイルス
小児喘息の急性増悪(発作)の約90%に何らかのウイルスが上気道で検出されることから、ウイルス感染症は喘息の重要な増悪因子と考えられています。
ヒトライノウイルス
喘息の急性増悪(発作)に関わるウイルス感染の約3分の2はヒトライノウイルスであると報告されています。
他にもエンテロウイルスやRSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、インフルエンザウイルスなどが検出されています。
運動
気道は温度差に敏感で、特に運動中の速い呼吸によって取り込まれる乾燥した冷たい空気が、運動誘発喘息の原因となります。症状が重い場合は軽い運動でも発作が起こります。特に、冬の乾燥した冷たい空気は特に発作を引き起こしやすいです。
運動による軽い発作は休息で改善されるため、気づかないこともありますが、診察でしっかりと確認することが大切です。運動誘発喘息があっても、適切な予防治療によりコントロールが可能で、活動範囲を広げることができます。
気象や環境
曇天、台風、気温の急変などの気象の変化は喘息発作のリスクを高める要因です。気温の急変については、前日と比較して3℃以上低下した日や過去5時間以内に3℃以上の気温低下があった場合に喘息の増悪が起こりやすいと言われています。
大気汚染物質、特にPM2.5や黄砂も喘息発作の誘因となり得ます。タバコの煙は多くの有害物質を含み、屋外での喫煙でも肺に煙が残留するため、禁煙が推奨されます。また、線香や蚊取り線香、花火の煙も喘息発作を引き起こすリスクがあります。
ストレス
身体的な疲労や睡眠不足、さらに心理的ストレスも、喘息発作の引き金となることがあります。
小児ぜんそく(気管支喘息)は治る?治療と予防について
適切な治療を継続すれば、多くの場合、日常生活に支障がない状態まで改善することが可能です。
しかし、一時的な治療では根本的な解決には至りません。「発作がないから」と勝手に薬を中止したり、不必要に多くの薬を服用したりすることは、喘息の治療に逆効果であり、副作用のリスクも伴います。医師の指示に従い、定期的に受診し、処方された薬を正しく服用することが重要です。
治療方法
小児喘息の治療は、症状や発作の有無、日常生活制限の有無、発作治療薬使用の有無といったコントロール状態を評価し、患者さん一人ひとりに合った治療薬を選択していきます。
診断は通常、複数回の喘鳴を観察した後に行われ、家族歴やアレルギー検査、薬の反応性などをみながら総合的に判断します。
治療は長期管理と発作時の対応に分かれ、長期管理には吸入ステロイドやロイコトリエン受容体拮抗薬などの抗アレルギー薬が、発作時には気管支拡張薬が用いられます。長期管理薬を使用していても症状が改善しない場合や悪化した場合は速やかに医療機関を受診することが推奨されます。
自宅できる小児ぜんそくの対策・予防
喘息発作の予防には、薬の服用だけでなく、アレルゲンを減らすための環境対策も大切です。
ハウスダスト、ダニ、カビなどのアレルゲンを抑えるためには以下のような対策が有効です。
- 定期的に部屋を清掃する
- カーペットやマットはできる限り使用しない
- 布団を日光に当てた後、掃除機でダニを除去する
- ぬいぐるみを置かない
- エアコンの清掃を定期的に行い、カビを防ぐ
- 毛の生えたペットを飼わない
- 同居者に禁煙してもらう