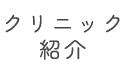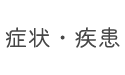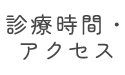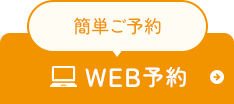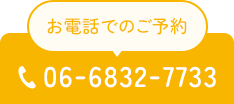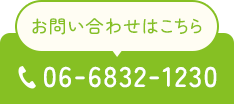子供の便秘にお悩みの方へ|原因・症状・解消法をわかりやすく解説
子供の便秘とは
 便秘とは便が長い時間出ないか、出にくい状態と定義されます。一般的には週に3回より少なかったり、5日以上出ない日が続けば便秘と考えます。毎日出ていたとしても、出すときに痛がって泣いたり、肛門が切れて血が出たりするような場合も便秘と考えます。
便秘とは便が長い時間出ないか、出にくい状態と定義されます。一般的には週に3回より少なかったり、5日以上出ない日が続けば便秘と考えます。毎日出ていたとしても、出すときに痛がって泣いたり、肛門が切れて血が出たりするような場合も便秘と考えます。
腸に便が溜まりすぎると、少しずつ便が漏れ出るようになります。うさぎの糞のような便や、柔らかい便が少しずつ1日に何回も出ている場合も便秘の疑いがあります。便秘のために治療が必要な状態を「便秘症」といい、便秘症が1~2カ月以上続いた場合は「慢性便秘症」といいます。子供の便秘は珍しいものではなく、10人に1人かそれ以上といわれています。離乳の開始や終了のタイミングや、トイレトレーニングのタイミング、通学開始時などに慢性便秘症が始まりやすいとされています。
子供の便秘は、便の回数だけでなく、様々なサインを総合的に判断する必要があります。具体的な状態を観察し、必要に応じて診察を受け、最適なケアと共に健康的な成長をサポートしましょう。お困りの場合は、当院にご相談ください。
正常な排便回数は?
正常な排便回数は月齢・年齢とともに変化します。
生後1か月では平均4回/日、生後3か月の母乳栄養児では平均3回/日、人工乳栄養児では平均2回/日です。2歳までに平均1~2回/日に減少し、3~4歳で1回/日となります。
子供は何日便秘が続くと危険?症状チェック
便秘症は、1週間に3回未満の排便、または5日以上排便がない状態です。毎日トイレに行くものの、小さく硬い便しか出ない、または排便時に痛みを伴う場合も便秘症に該当します。便秘症を放置すると、長期的な排便障害や成人してからも便秘の問題が続くリスクが高まります。
このような症状はありませんか?
1歳の赤ちゃんでも便秘になることは珍しくありません。便秘の兆候として、以下のような症状が見られることがあります。
- ぐずり続けている
- 活力がない
- 食欲不振
- トイレを避ける
- おならが多く、強い臭いがする
- 粘り気のある便が出る
- 便を我慢する様子が見られる
- 下着に汚れが付くことがある
- 便意を感じても、足を絡めて我慢する
便秘は快適な排便ができないことから悪化することがあり、子供の場合、大人とは異なる症状が現れることがあります。以下の症状に注意し、子供が便秘でないかを確認してください。
子供の便秘を放置しておくのは危険?
 便秘症は放置しておくとだんだん悪くなることが多い病気です。その理由を解説します。
便秘症は放置しておくとだんだん悪くなることが多い病気です。その理由を解説します。
硬い便を出して肛門が切れ、痛い思いをすると、子供は次の排便を我慢したり、肛門の筋肉を締めつついきんだりするようになります。極端な例では足をクロスさせて便を我慢します。便はしばらく我慢していると便意が治まるため、そのまま大腸に残ります。大腸は便から水分を吸収してしまうので、便はどんどん硬くなってしまい、いよいよ排便する際により強い痛みを伴うことになり、子供はますます便を我慢するといった悪循環に陥ります。
また、このようなことが続くと、常に便が直腸にある状態が続くことになり、直腸がだんだん鈍感となってしまい、便意が生じにくくなります。便意が生じにくくなる結果、ますます便が長く腸にとどまり硬くなっていくのです。
このような二重の悪循環により、子供の便秘症は放置すると悪くなっていくと考えられています。
便秘症の診断
便秘症は、便の回数、硬さなどを聞くことで診断しますが、必要に応じて、腹部X線撮影や超音波検査を行う場合もあります。診断の第一歩は、便秘症であるかどうかの確認です。先に触れたように、便の回数が少ないか、便を出すのに苦痛を感じれば便秘と考えます。
注意が必要なのは、うさぎの糞のようなコロコロした便や、柔らかい便が少しずつ1日に何回も出ている場合です。このような場合には、腸に便が溜まり過ぎて、漏れ出るようになっている可能性があり、便秘が疑われます。便秘が1~2ヵ月以上続いている場合には「慢性便秘症」といい、治療が必要となります。
一方、普段は便がよく出ている子供が、一時的に便秘の状態になっただけの時は「一過性便秘」といいます。一過性便秘の場合には、浣腸や薬で便を出してあげれば、また元の良い状態にもどる場合がほとんどで、「慢性便秘症」とは違うものです。
「慢性便秘症」と診断された場合、消化管の解剖学的異常を含め器質的な原因がないか調べることも重要です。
慢性便秘症をきたしうる、なにか特別な原因がある場合にみられる徴候
- 胎便が生後24時間以内に出なかった
- Hirschsprung病の家族歴
- 成長障害や体重減少がある
- 繰り返し嘔吐がみられる
- 血便がある
- 下痢(軟便)が頻繁に出る
- 腹部膨満(お腹が張っている状態)がある
- 肛門の形や位置がおかしい
- 直腸肛門指診の異常がある
- 脊髄疾患を示唆する神経所見と仙骨部の皮膚所見がある
便秘の原因となる病気の中で、特に重要なものは、鎖肛とHirschsprung病です。どちらも先天性の病気で、鎖肛は肛門がちゃんと開いていないために便が出ない病気です。Hirschsprung病の場合、肛門は正常ですが、腸の肛門に近い部分がいつも収縮している状態なために便が出ない病気です。どちらも生まれつき症状があり、普通の治療ではなかなかよくならないことが多いので、生まれつきの便秘や、頑固な便秘には注意が必要です。ただし、Hirschsprung病の場合にはそれほど症状が強くないこともあり、1歳をすぎてからようやく診断されるようなこともあります。
特別な原因がない場合は「慢性機能性便秘症」と呼ばれ、以下で「慢性機能性便秘症」の治療に関して説明していきます。
便秘を悪化させることがあるもの
- 育児、生活状況の問題
- 強制的なトイレットトレーニング、トイレ嫌い、学校トイレ忌避、親の過干渉、性的虐待、家庭環境の変化、いじめなど
- 便量の減少と乾燥
- 低食物繊維食、慢性的な脱水、低栄養、栄養失調
子供の便秘解消法
適切に治療を行えば数日から2カ月で「週に3回以上快適に便が出る」状態になります。その状態を続けていると1~2年で便秘症が治ることも少なくありません。大人になるまで治療を続ける必要がある場合もありますが、生活や食事に気を付け、正しく薬を内服していれば快適に暮らせます。また治療は早く始めたほうが、あとの経過が良くなるといわれています。慢性機能性便秘症と診断したら、次に直腸に便が溜まっていないか確認します。以下のような症状がある場合は便が多量に溜まっている可能性があります。
- 少量の便が頻繁に出る
- いきんでいるが出ない
- 最後の排便か5日以上排便がない
- 診察で腹部に便塊を触れる
- 直腸診(肛門から指をいれること)で便塊を触れる
- 腹部X線や超音波検査で直腸に便塊がみられる
便が多量に溜まっている状態では様々な治療の効果があがらないため、まずはその便塊を排出することが必要です。
溜まった便を出す(便塊除去、ディスパンクション)
腸に溜まった便は浣腸や飲み薬で出します。浣腸はすぐに効果が得られ、子供がすぐに楽になり、効果をその場で確認できるメリットがあります。しかし、硬い便をそのまま出すため、肛門が切れて痛い思いをする可能性もあります。医療機関での処置に恐怖心を抱いている子供で、すぐに出さなくてもよい場合は下剤を選択することもあります。
それでも出ない場合は腸を洗ったり(洗腸)、指で便をかき出したり(摘便)します。あまりにも便が硬く大量であれば麻酔をかけて処置しないといけない場合もあります。
洗腸や摘便は子供にとって辛い処置ですし、麻酔の危険もあるため、そうなる前に対処することが重要です。
維持療法
硬い便を無事に出せた後は、再び溜まることがないように維持療法を行います。
維持療法は生活習慣や排便習慣の改善、食事療法、薬物療法を3本柱として行っていきます。こどもの便秘に普通に使われる薬はいずれも安全性が高く、「クセ」になることは全くない、もしくはほとんど問題になりません。便秘の状態が続いているより、はるかに安全で、長い目でみても良いことです。
生活習慣の改善
すぐに目に見えて効果が感じられるものではありませんが、便秘の治療としてだけでなく、子供の健康にとって良いことなので、ぜひ実践してみてください。
- 早寝早起きをして、規則正しい生活をする
- バランスのとれた食事を3食きちんととり、決められたおやつの時間以外には間食を避けるようにする
- 散歩や掃除など軽い運動でもいいので身体を使う(身体を動かすことで、腸の運動も促されるため便通が良くなるといわれています。)
トイレットトレーニングについて
無理なトイレットトレーニングは、便秘を悪化させる場合もあれば、便秘の原因になることもあります。子供はトイレですることが嫌で排便を我慢してしまうことがあります。また、失敗した時にしかったりすると、その意味が理解できず、しかられないために排便を我慢することを選ぶことがあります。
幼児期のトイレットトレーニングは本人の発達段階(ひとりで歩け、ひとりで下着の上げ下げができる。コミュニケーションがある程度とれる。おしっこやうんち、トイレに興味を示す。人のまねをしたがる。など)を考慮して開始します。
便秘の場合はまず便秘の治療を受け、規則的な排便習慣が十分ついてからトイレットトレーニングを始めるようにしましょう。
トイレで排便できない場合、はじめのうちは着衣のまま便座やオマルに座らせても構いません。排便しなくても5~10分座っていることができたらほめてあげたり、ごほうびをあげたりしましょう。
食事療法
食事療法がどれくらい便秘に効果があるかは、子供によって異なるようではっきりわかっていません。しかし、下記のような「食事の注意」も、生活習慣と同様に健康に良いことなので、ぜひ実践してみてください。
適切な食事量
食事摂取(乳児では哺乳)の全体量を見直し、年長児では無理なダイエットをしていないかを確認します。
適切な水分量
水分が不足していれば便秘の原因になります。運動時にはこまめに水分をとることや、乳幼児で多量の寝汗がみられる場合に夜間の着せ過ぎを改めることで便秘が改善することもあります。ただし、脱水していないのに、余分に水分をとらせても便秘に効果はありません。便秘だという理由だけで赤ちゃんに白湯を与えることはお勧めしません。
食事内容
便秘の改善には食物繊維が有効ですが、特定の食品を過剰に摂取するよりも、バランスの取れた食事が重要です。食物繊維は腸内の善玉菌を増やし、蠕動運動を促進することで便通を良くします。リンゴ、バナナ、キウイ、スイカ、メロン、ひじき、わかめ、さつまいも、にんじん、ほうれん草、プルーンなどが良い食物繊維源です。表に繊維の量を示します。米国では、1日に「年齢+5g」の繊維をとることが勧められています。

研究によると、便秘の子供とそうでない子供の食事における食物繊維や水分の摂取量に大きな差はなく、海外のガイドラインでも通常の摂取量が推奨されています。したがって、無理なく栄養バランスを考えた食事を提供することが、子供の便秘改善に役立ちます。
薬物療法
便が腸内に長く留まると硬くなり、排便時に痛みを感じることがあります。これにより、子供たちは排便を苦痛と感じるようになることがあります。そのため、当院では子供達が排便を快適なものと感じられるよう、薬物療法を通じて排便を助けることがあります。この治療では、便を柔らかくする薬、大腸の機能を正常化する薬、浣腸、漢方薬などが処方されます。
お通じ日記
長期にわたる便秘の場合、排便の回数や形状を記録することは有効ですが、子供が好むキャラクターのノートやシール、スタンプを使って記録を楽しむ方法もお勧めです。
このようにして、排便をポジティブに捉えられるようになれば、治療がよりスムーズに進んでいくことが予想されます。
参照
小児慢性機能性便秘診療ガイドライン作成委員会作成「こどもの便秘-正しい知識で正しい治療をー」