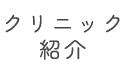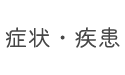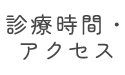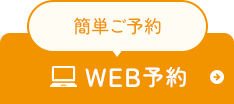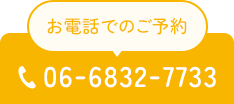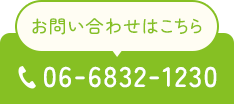- マイコプラズマ感染症とは?
- マイコプラズマ感染症の主な症状
- マイコプラズマ肺炎とは?流行ってる病気?
- マイコプラズマ肺炎の症状チェックリスト
- マイコプラズマ肺炎を早く治すには?
- マイコプラズマの感染経路|家庭内や学校でうつる?
- マイコプラズマ感染症はいつまでうつる?登校・登園の目安
- マイコプラズマ感染症の検査方法と診断の流れ
- マイコプラズマ感染症の治療法|薬は効く?
マイコプラズマ感染症とは?
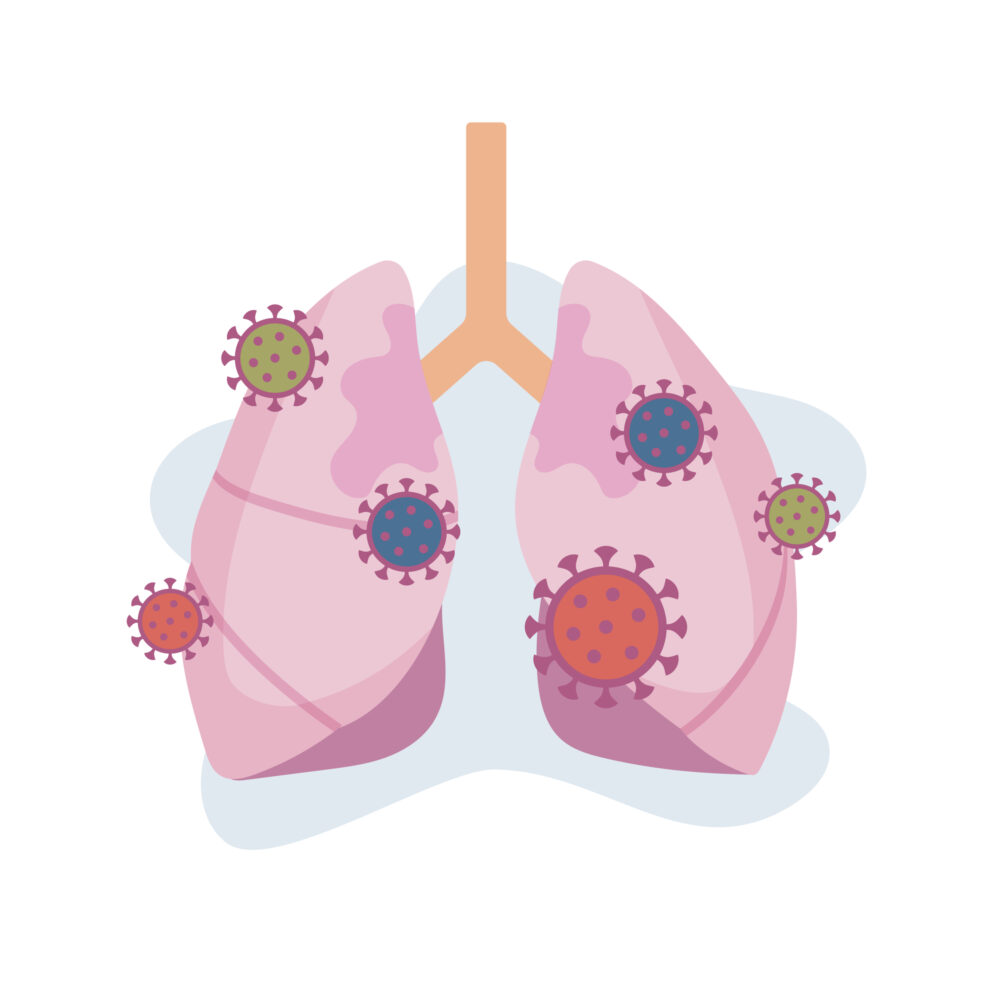 マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマという微生物が原因で、ほとんどの場合は下気道感染症(肺炎や気管支炎)として発症するが、感染後の免疫応答により肺外病変(皮疹や溶血性貧血、多発性関節炎、膵炎、肝炎、心外膜炎、心筋炎、髄膜脳炎)など多様な症状を引き起こす感染症です。飛沫感染によりご家庭や学校で感染し、2~3週間の潜伏期の後に発症することが多いです。
マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマという微生物が原因で、ほとんどの場合は下気道感染症(肺炎や気管支炎)として発症するが、感染後の免疫応答により肺外病変(皮疹や溶血性貧血、多発性関節炎、膵炎、肝炎、心外膜炎、心筋炎、髄膜脳炎)など多様な症状を引き起こす感染症です。飛沫感染によりご家庭や学校で感染し、2~3週間の潜伏期の後に発症することが多いです。
マイコプラズマ感染症の主な症状
マイコプラズマ感染症は、2~3週間の潜伏期間を経て発症することが特徴で、風邪やインフルエンザと比べて潜伏期間が長いです。潜伏期間が長いため、地域ごとに流行する傾向があります。発症すると以下の症状が起こります。
- 発熱
- 頭痛
- 倦怠感
- 咽頭痛
- 嗄声
- 筋肉痛
- 関節痛
- 乾性咳嗽
- 皮疹(肺外病変として最多)
マイコプラズマ感染症は、他の症状に比べて咳が遅れて現れることが多く、発熱が治まった後も持続することが多いです。初期には乾いた咳が特徴ですが、徐々に痰を伴う咳に変わり、特に夜間に悪化する傾向があります。
小中学生における肺炎の主な原因であり、成人や乳幼児にも感染することがあります。重症化し肺炎を併発するリスクもあるため、熱や咳が長引き、元気がなく食欲が落ちるような症状が見られる場合は、すみやかに受診することをおすすめします。
マイコプラズマ肺炎とは?流行ってる病気?
 マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという病原体による感染が肺に及び、炎症を引き起こす呼吸器系の疾患です。この感染症は急性上気道炎で終わる場合もあれば、気管支炎や肺炎を発症することもあります。特に若年層に多く見られ、15歳以下の感染者が全体の80%を占めていますが、60歳以上では感染者は少ないです。1年を通じてみられますが、秋冬に増加する傾向があります。マイコプラズマ肺炎は、長引く咳が特徴的で、レントゲンで確認できる肺炎の影に比べて肺の聴診所見が少ないため、「非定型型肺炎」とも呼ばれます。多くの場合、入院せずに通院治療で対応可能です。
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという病原体による感染が肺に及び、炎症を引き起こす呼吸器系の疾患です。この感染症は急性上気道炎で終わる場合もあれば、気管支炎や肺炎を発症することもあります。特に若年層に多く見られ、15歳以下の感染者が全体の80%を占めていますが、60歳以上では感染者は少ないです。1年を通じてみられますが、秋冬に増加する傾向があります。マイコプラズマ肺炎は、長引く咳が特徴的で、レントゲンで確認できる肺炎の影に比べて肺の聴診所見が少ないため、「非定型型肺炎」とも呼ばれます。多くの場合、入院せずに通院治療で対応可能です。
- 乾いた咳が長引く
- 熱が平熱に戻らない
これらの症状が見られる場合は、マイコプラズマ肺炎の可能性があるため、速やかな医療機関への受診が推奨されます。また、マイコプラズマ肺炎は一度感染しても完全な免疫が形成されにくいため、再感染することがあり、本邦では4年ごとの周期でオリンピックのある年に流行を繰り返してきましたが、近年この傾向が崩れつつあります。
また、2020年には新型コロナウイルスの影響で患者数が少なかったものの、2024年には日本国内で患者数が増加しており、中国や韓国でも流行が確認されています。さらに、抗生剤の過剰使用により耐性菌が増え、特にマイコプラズマ治療に使われるマクロライド系抗生剤への耐性率が高くなっています。日本でもマクロライド系抗生剤の使用割合が高いため、耐性菌による感染拡大のリスクがあることを認識する必要があります。
マイコプラズマ肺炎の症状チェックリスト
マイコプラズマ肺炎の症状は、一般的な風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症と似ているため、初期段階での診断が難しい場合があります。下記の様な症状が当てはまる場合、お早めに医療機関を受診してください。
- 長引く乾いた咳
- 発熱
- 倦怠感
- 喉の痛み
- 呼吸困難
マイコプラズマ肺炎を早く治すには?
2024年現在、マイコプラズマ肺炎は特別な迅速治療法はありません。治療開始後、多くの場合は数日~1週間で症状が改善しますが、回復には個人差があり、数週間かかることもあります。
また、感染後咳嗽(感染の後の咳)として、咳が数日から数週間続くことがあります。症状が治まり元気が戻ったら、通常の生活に戻っても問題ありません。
マイコプラズマの感染経路|家庭内や学校でうつる?
 マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマという細菌によって引き起こされ、風邪に似た初期症状を示します。この感染症は風邪と同様の感染経路をたどり、主に飛沫感染によって人から人へと広がります。
マイコプラズマ感染症は、マイコプラズマという細菌によって引き起こされ、風邪に似た初期症状を示します。この感染症は風邪と同様の感染経路をたどり、主に飛沫感染によって人から人へと広がります。
接触感染
病原体が付着した手で目や口、鼻などの粘膜に触れることで起こることがあります。日常生活でよく使われるお箸、バスタオル、歯ブラシなどは、特に共有を避けた方が良いでしょう。
飛沫感染
感染者の唾液や唾が含まれる咳やくしゃみによって病原体が飛散し、これを他の人が吸入することで感染が広がるパターンです。
風邪ほどの感染力はありませんが、保育園、学校、家庭などの集団生活環境では流行しやすいとされています。
マイコプラズマ感染症はいつまでうつる?登校・登園の目安
マイコプラズマ感染症は、特に子供の間で流行することが多い病気で、この感染症は、主に咳やくしゃみを通じて飛沫感染し、症状が始まる前から他人にうつす可能性があります。感染後の適切な対処と登校・登園の目安を理解しておくことが重要です。
潜伏期間と感染力
マイコプラズマ感染症の潜伏期間は2~3週間です。感染力は非常に強いわけではなく、家族間での感染も必ずしも起こりません。主に5~10歳の子供に多く見られ、以前は4年ごとのオリンピック年に流行する傾向がありましたが、最近はそのパターンは見られず、秋から冬にかけて地域的に小規模な流行が見られます。
登校・登園の目安
マイコプラズマ感染症にかかった場合、次の点に注意して登校・登園を判断することが推奨されます。
発熱が治まり、全身状態が良好であること
通常、発熱している間は自宅で安静に過ごすことが望ましいです。
強い咳が収まっていること
咳が続く間は他人に感染させるリスクが高いため、咳が治まるまで登校・登園を控えることが重要です。
食欲が戻っていること
全身状態が良好で、食欲が戻っていることも登校・登園の目安とします。
医師の許可を得ること
明確な出席停止期間は定められておらず、症状が軽快したら登校・登園可能となります。
回復しているのか不安な場合はご相談ください。
マイコプラズマ感染症の検査方法と診断の流れ
問診で症状をお伺いし、必要に応じて検査を実施します。
血液検査
感染初期には陽性が出にくいため、急性期と回復期の2回に分けて採血するのが望ましいです。この検査では、マイコプラズマ抗体価や、炎症反応に関連するタンパク質(CRP)や白血球の値を測定します。
画像検査
画像検査では、胸部X線やCTにて、気管支炎や肺炎に至っていないか確認します。画像所見は肺炎様の所見から胸水貯留、肺門部リンパ節腫脹など多彩なため、他の検査と組み合わせて診断していきます。
迅速検査
迅速検査は、綿棒で喉の粘膜をぬぐい取り、専用キットで検査する方法です。15分程度で結果が出ますが、感度が低いため、他の検査結果や問診をもとに診断が行われます。
マイコプラズマ感染症の治療法|薬は効く?
マイコプラズマ感染症の治療ですが、下記の方法があります。
第一選択薬はマクロライド系の抗菌薬(クラリスロマイシンやアジスロマイシンなど)です。クラリスロマイシンは1日2回の内服でよいですが、10日間の内服が必要です。一方アジスロマイシンは1日1回の内服で3日間内服すれば1週間効果が持続するため、当院としてはアジスロマイシンの内服をお勧めしています。ただ、アジスロマイシンは苦みがあり内服が難しい場合もあるため、当院では一緒に飲むと内服しやすいものなどをお伝えするようにしています。
近年マクロライド耐性のマイコプラズマが問題となっていますが、マクロライド耐性菌は感受性菌に比べて発熱期間が数日長いものの、通常は重症化せずに軽快することが多いと言われています。そのため、基本的には第一選択薬はマクロライド系の抗菌薬であり、学童期以降で永久歯に生え変わっている場合にはドキシサイクリンやミノサイクリンといった抗菌薬を選択しています。従来のマクロライド系抗菌薬でも効果が得られない乳幼児に対してはトスフロキサシンというニューキノロン系の抗菌薬を選択する場合もあります。