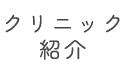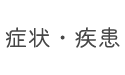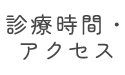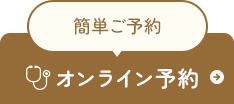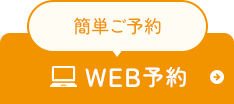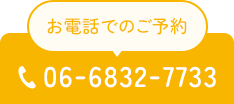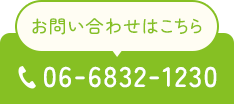起立性調節障害(OD)の治し方は?症状・原因・親として子供にできることの解説
起立性調節障害(OD)は、思春期の子供に多く見られる体調不良で、朝起きられない・立ちくらみがするなどの症状が続きます。 「怠けてるのでは…?」と誤解されやすい病気ですが、適切な理解とサポートが回復への鍵となります。
本記事では、ODの原因や治し方、親としてできる具体的なサポート方法について解説します。
起立性調節障害(OD)の診療では、お一人おひとりのお話をじっくり伺い、丁寧に向き合うお時間が必要となります。
そのため、十分な診療時間を確保させていただく目的で、OD診察をご希望の方はネット予約ではなく、【お電話でのご予約】をお願いしております。
初めての方や、親御さんのみでのご相談の場合も、どうぞお気軽にお電話ください。
- 小・中学生に多い「起立性調整障害」(OD)とは
- 起立性調節障害(OD)の症状
- 起立性調節障害(OD)の原因
- 起立性調整障害(OD)は不登校の原因になる?
- 起立性調節障害(OD)の診断
- 起立性調節障害(OD)の治し方
- 起立性調節障害(OD)の子供に対して親が出来ることはある?
- 起立性調節障害(OD)に関するQ&A
小・中学生に多い「起立性調整障害(OD)」とは
 起立性調節障害(OD ; Orthostatic Dysregulation)は身体全体のバランスを整える自律神経機能が低下している状態です。自律神経は心臓や脳、全身の血液循環、水分栄養の消化吸収、体温、睡眠などのバランスをコントロールしています。循環器系の機能が正常に働かず、立ち上がる際に、血圧低下や心拍数の異常な増加が見られます。ODで一番問題となるのは、脳血流が低下することです。その結果、立ちくらみやふらつきという低血圧症状だけでなく、脳の機能が悪化します。記憶力、思考力、集中力の低下などは、中等症以上のODでは必発といっても過言ではありません。
起立性調節障害(OD ; Orthostatic Dysregulation)は身体全体のバランスを整える自律神経機能が低下している状態です。自律神経は心臓や脳、全身の血液循環、水分栄養の消化吸収、体温、睡眠などのバランスをコントロールしています。循環器系の機能が正常に働かず、立ち上がる際に、血圧低下や心拍数の異常な増加が見られます。ODで一番問題となるのは、脳血流が低下することです。その結果、立ちくらみやふらつきという低血圧症状だけでなく、脳の機能が悪化します。記憶力、思考力、集中力の低下などは、中等症以上のODでは必発といっても過言ではありません。
発症年齢と好発時期
ODは小学校高学年から中学生に多く、午前に症状が強いため学校生活に支障をきたすことがあります。重症例では不登校やひきこもりになってしまい、その後の社会復帰にも大きな支障をきたすことがあります。 ODの有病率は軽症例も含めて中学生の約10%と多くの子供たちを苦しめている病気で、不登校の約3-4割にODが併存することから、家族だけでなく学校の理解も大切になります。発症の早期から重症度に応じた適切な治療と家庭生活や学校生活における環境調整を行い、適正な対応を行うことが不可欠です。
当院にも多くのODのお子さんが通院されています。当院としてはお子さんの状態が少しでも良くなっていくよう、全力でサポートさせていただきたいと考えています。本人の受診が難しい場合など、まずは親御さんだけでも来院いただき、ご相談いただければと思います。
大人にも起こる起立性調節障害
 起立性調節障害(OD)は10歳~16歳の思春期に多く発症し、この時期には身体の変化が自律神経に影響を及ぼすことがあります。ただし、ストレスが多い生活を送ると、大人になってからも起立性調節障害を発症するリスクがあります。大人での症状は子供と似ており、朝起きるのが困難であったり、午前中の集中力の低下や立ち上がる際のめまいや動悸が起こったりすることがあります。さらに、パーキンソン病や認知症などの神経疾患でも起立性調節障害の症状が見られることがあります。
起立性調節障害(OD)は10歳~16歳の思春期に多く発症し、この時期には身体の変化が自律神経に影響を及ぼすことがあります。ただし、ストレスが多い生活を送ると、大人になってからも起立性調節障害を発症するリスクがあります。大人での症状は子供と似ており、朝起きるのが困難であったり、午前中の集中力の低下や立ち上がる際のめまいや動悸が起こったりすることがあります。さらに、パーキンソン病や認知症などの神経疾患でも起立性調節障害の症状が見られることがあります。起立性調節障害(OD)の症状
起立性調節障害は、以下のような症状や特徴を示すことがあります。
-
立ちくらみ、あるいはめまいを起こしやすい
-
立っていると気持ちが悪くなる、ひどくなると倒れる
-
入浴時あるいは嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる
-
少し動くと動悸あるいは息切れがする
- 朝なかなか起きられず午前中調子が悪い
-
顔色が青白い
-
食欲不振
-
へそ周囲に強い痛みをときどき訴える
-
倦怠あるいは疲れやすい
- 頭痛
- 乗り物に酔いやすい
起立性調節障害(OD)の原因
起立性調節障害(OD)はさまざまな要因が組み合わさって発症します。主な原因は以下の通りです。
起立時の自律神経による血圧調整機能の破綻
立ち上がったときに血圧を維持する働きがうまくいかず、脳への血流が低下します。
交感神経の働きすぎ、または働き不足
自律神経の一種である交感神経が過剰、または不足して反応し、血圧や心拍数の調整が乱れます。
水分不足
体内の水分が不足すると血液量が減り、脳への血流がさらに低下しやすくなります。
心理社会的ストレス
学校や家庭でのストレスが身体に影響し、症状を悪化させることがあります。
例:身体がつらくても登校しなければならないプレッシャーなど。
日常活動量の低下
運動不足により筋力と自律神経機能が低下し、血液循環が悪化する悪循環が生まれます。
起立性調整障害(OD)は不登校の原因になる?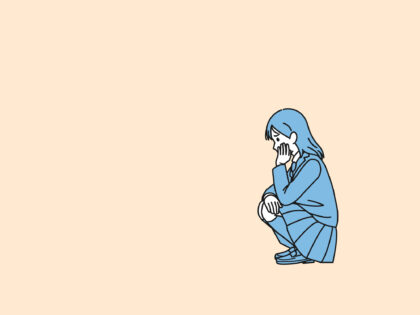
起立性調整障害(OD)は、以下の理由で不登校に繋がりやすいとされています。
朝起きるのが難しい
起立性調整障害(OD)の症状は朝に強く出ることが多く、特に朝起きるのが難しいため、学校に行くことが困難になります。
体調不良
頻繁な立ちくらみや疲労感、頭痛、腹痛などがあるため、長時間座って授業を受けるのが難しくなることがあります。
心理的影響
継続的な体調不良や学校生活への適応困難がストレスとなり、心理的にも不安や抑うつ状態に陥りやすくなります。
社会的孤立
頻繁に学校を休むことにより、友人との交流が減り、社会的孤立を感じやすくなります。
起立性調節障害(OD)の診断
起立性調節障害(OD)の疑いがある場合、先に挙げた11の症状のうちで3つ以上が当てはまるか、2つの症状があって疑わしいと思われる際には、詳細な検査を行います。これには血液検査(電解質、腎機能、肝機能、甲状腺機能の検査)、尿検査、心電図、胸部レントゲンなどが含まれます。
他の病気を除外できた場合に起立性調節障害(OD)を疑い、「新起立試験」を実施してサブタイプの特定や重症度の評価を行います。
- 起立直後性低血圧(INOH): 起立直後に血圧が急激に下がり、回復も遅い状態です。
- 体位性頻脈症候群(POTS): 起立時に血圧は低下せず、心拍数が顕著に増加します。通称「ポッツ」とも呼ばれます。
- 血管迷走神経性失神(VVS): 起立中に突然、収縮期と拡張期の血圧が低下し、起立失調や意識消失発作が生じます。
- 遷延性起立性低血圧(delayed OH): 起立直後は血圧と心拍が正常ですが、起立して3〜10分後に収縮期血圧が臥位時より15%以上、または20mmHg以上低下します。
次に「心身症としてのOD」診断チェックリストを使い、心理社会的関与があるのかどうかを判定します。
起立性調節障害の治し方
治療は、以下のステップを組み合わせながら進めます。
- ① 疾病教育
- ➁ 非薬物療法
- ➂ 学校との連携
- ④ 薬物療法
- ⑤ 環境整備(友人・家族)
- ⑥ 心理療法
お子さんのお話をじっくり伺った上で、それぞれに合った治療方法をご提案します。
受診への抵抗感がある場合も、まずはお話だけでも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。
疾病教育
起立性調節障害(OD)の症状に対して、ODへの理解がない方は「気持ちの持ちよう」と考えがちですが、そうではありません。治療の第一歩は「ODは起立循環障害という特徴のある病気であり、根性論はいったんおいといて、身体的治療から始める」という認識を持つことです。
例えば下記のような病気の特徴を学んでおくことが大切です。
- 立ち上がったときに血圧低下や脳血流低下を起こすため立ち眩みや頭痛が起こる
- ひどくなると倒れることもある
- 少し動くだけで動機がする
- 身体を横にしたり頭を下げたりすると楽になる
- 症状は午前中にひどく、午後から徐々に回復するという日内変動がある
- 夜はなかなか寝付けない
- 季節や天候によって症状が変化する
- ODになりやすい遺伝的体質がある
- 心理的ストレスによって症状が悪化する
Column:ODの子供に対する禁句
起立性調節障害のお子さんに接するうえで、周囲の声かけはとても大切です。
しかし、悪気はなくても、無意識のひと言が子供を追い詰め、症状を悪化させることがあります。
特に、次のような言葉には注意が必要です。
-
「朝起きられないのは、夜遅くまでスマホをしているからだ!」
-
「朝はしんどいといって遅刻するのに、夜元気なのは根性が足りないからだ!」
-
「ゲームできるんだから勉強もしなさい!」
-
「少しくらいしんどくても学校に行けるでしょ!」
-
「学校に行かないと、落ちこぼれてしまうぞ!」
-
「このままでは一生引きこもりになってしまうぞ!」
非薬物療法
すぐにできる日常生活での工夫や注意点があります。薬物療法を開始する前(もしくは同時)に行っていきます。
日常生活での工夫
- 日中は身体を横にしないようにします。だるいからと身体を横にしているとODがさらに悪化します。寝そべりスマホはやめてください。
- 起立時にはいきなり立ち上がらず、お辞儀をするように前かがみになりながら30秒ほどかけてゆっくり立ち上がるようにしてください。急激な脳血流低下を防ぎ、立ち眩み、ふらつき、頭痛を軽減することができます。
他にもすぐに実践できる工夫があり、当院では患者さんの状態に合わせてお伝えするようにしています。
運動療法
どのような運動が ODに効果的なのか、まだエビデンスは多くありません。運動するに越したことはありませんが、その方の状態によってどんな運動から始めたらいいかは異なります。当院ではこれまでの治療経験から出歩くことが可能な方に対して、下記のようにウォーキング(速足での散歩)をおすすめしています。
(例)できるだけ毎日、ウォーキング(速足での散歩)をしてください。最初は1日10~15分からで構いません。登下校時の歩行を含めて1日の合計で少なくとも約60分を目標に、少しずつ増やしていくことが大切です。
しかし、午前中の調子が悪く、学校を休んだために屋外での活動が憚られる場合などは、屋内で実践可能で効果的な運動も提案させていただいております。いつでもご相談ください。
水分や食塩の摂取
- 水分はこまめに摂取することが大切です。1時間にコップ1杯など、時間を決めておくと実行しやすいのでおすすめです。1日1.5~2Lを目安にして、汗が多い日などはその分を補うようにしてください。
- 食塩は1日10~12gを目安にしてください。臥位(身体を横にした状態)での血圧が正常であれば、その必要はありません。
学校との連携
ODの子供は朝に身体を起こせないため、遅刻や欠席になりがちです。学校での環境整備が通学のしやすさに直結するため、学校関係者(主に担任の先生)と連携を図ることも大切です。
親御さんからの了承が得られれば、当院から学校に対して病状説明を行い、学校で行っていただきたい配慮などをお伝えすることも可能です。
当院からお願いしたことがある具体例は下記のとおりです。
- ODは身体の病気で特に午前中に悪化するため、朝の起床困難、起立困難が生じ、遅刻や欠席しやすくなってしまいます。体調が回復してから登校する必要があり、登校できたとしても、一旦は別室で体調を整えてから教室に合流するなどの配慮をお願いします。
- 水分摂取は1時間毎に行う必要があり、授業中や体育の授業でも水分補給を行うよう促してください。
- 体育の授業は体調に応じて実施可能ですが、見学させる場合は日陰または屋内の過ごしやすい環境で見学させるようにしてください。
- 気分不良が生じた場合、脳血流低下を防ぐため、必ず臥位にするようにしてください。
- 子供本人から同意を得ることができれば、クラスでODという病気を取り上げてください。(なぜ遅刻・早退するのか、クラスのみんなが理解することで心理的ストレスによるODの悪化を防ぐことができます。)
薬物療法
疾病教育、非薬物療法、学校との連携を行った上で、効果が得られない場合に薬物療法を併用していくことになります。薬物療法だけでは十分な効果は得られません。
サブタイプや重症度によって使用する薬剤や量が異なります。また薬物療法を開始してもすぐに効果が現れることは少ないです。中等症や重症の場合、効果が現れるには通常でも2~3か月以上かかります。楽にならないからといってすぐにやめないようにしてください。
環境整備(友達や家族)
遅刻や早退を繰り返している子供(中等症~重症)は、自分の身体症状に対して強い不安感を感じています。また学業などの遅れから、友達との疎外感で焦りを感じている場合も多いです。さらに保護者や家族、あるいは学校の先生側に病気の理解が乏しいと、「怠け者」や「仮病」、「頑張りが足りない」などの烙印を押され、自宅や学校での居場所がなくなり、精神的に追い詰められ部屋にひきこもるようになってしまいます。その結果、運動不足や昼夜逆転生活に陥り、ODの病状がますます悪化する悪循環となってしまいます。
この悪循環が生じているODでは、環境整備を十分行う必要があります。その基本は、保護者と学校関係者(担任の先生)がODの病態や発生機序を十分理解し、子供への接し方を改めることです。学校では校長先生含め、すべての教員にODについての疾病理解を深めてもらうことが大切です。たった一人の教員に理解がなかったために、ODの子を叱りつけてしまい、完全に不登校に陥ったケースもあります。最近では以前に比べ学校関係者の理解が非常に進んでおり、このような悲劇は少なくなってきています。
治療には長期間を要します。医療、家庭、学校が協力し、焦ることなく「子供を信じて見守る」ことが大切です。
心理療法
通常は軽症~中等症のODであれば心理療法は必要ありません。重症の場合は心理療法を実施する場合があります。また神経発達症(発達障害)が併存している場合なども、心理療法を実施することがあります。心理療法には様々な技法があり、基本的にはカウンセリングが中心です。カウンセリングは医師が行う場合もありますが、通常は心理士にお願いすることになります。時間をしっかりとって行うため、一般外来で行うことはありません。
起立性調節障害(OD)の診療では、お一人おひとりのお話をじっくり伺い、丁寧に向き合うお時間が必要となります。
そのため、十分な診療時間を確保させていただく目的で、OD診察をご希望の方はネット予約ではなく、【お電話でのご予約】をお願いしております。
初めての方や、親御さんのみでのご相談の場合も、どうぞお気軽にお電話ください。
起立性調節障害の子供に対して親が出来ることはある?

起立性調節障害においては、お子さんの感情に共感し、サポートすることが非常に重要です。親御さんからの厳しい言葉がお子さんにストレスを与え、治療の障害となることがあるため、お子様が学校に行ける時間や日数に応じて柔軟に対応し、無理のない範囲で学校生活を送れるようにサポートしましょう。
起立性調節障害の治療には、水分や塩分の適切な摂取、起き上がり方の工夫が重要とされており、これらは親が積極的にサポートできる領域です。また、お子さんが怠けているわけではなく、体の調節機能の障害によって症状が発生していることを理解し、責めることなく支えることが大切です。
不登校や引きこもりに至った場合は、親が焦ることなく、医療機関や学校と連携し適切なサポートを続けることが重要です。問題を一人で抱え込まずに、早期に医療機関や学校に相談することも推奨されます。
起立性調節障害(OD)に関するQ&A
夜に早く就寝したら朝に起きることは可能ですか?
夜に早く寝て朝に起きられるのは、起立性調節障害(OD)ではない子供、もしくはODでも軽症のお子さんです。
朝に起きられない原因として、下記2つの理由が考えられています。
① 睡眠覚醒リズムの乱れ
② 交感神経機能の活性の低下(特に午前中の)
朝起床して登校したほうがいいですが、自律神経機能が改善していない状態で無理矢理起こして登校させても、かえって心身に負荷がかかり、ODが治りにくくなります。
子供が「遅刻したくないから起こしてほしい」と言ってきます。無理矢理起こしてもいいのでしょうか?
「起こしてほしい」という言葉が本心かどうかは難しいところです。基本的にODの子供は身体が怠いので、本心は「ゆっくり寝かせてほしい」場合が多いです。
起こすかどうかはODの重症度によって異なります。
軽症の場合は本人からの「起こしてほしい」という言葉がなくても、保護者が遅刻しないように声かけをして起こしましょう。
中等症~重症の場合は無理に起こしても自律神経機能の悪さから、全身倦怠感、頭痛などが起こり、登校したところで1日中辛いままであり、かえってODが悪化してしまいます。
それでも「遅刻したくない」、「試験があるから絶対に起こしてほしい」などと子供が言う場合は、起床時間や起こすための声かけのルールを親子で話し合って決めるようにしてみてください。
ルールどおりの声かけで起きなければ、それ以上は声かけをしないようにします。
親子で事前にルールを決めておき、親子関係の悪化を防ぐようにすることも大切です。
ゲームやスマートフォンの使用はやめたほうがいいですか?
ゲームやスマートフォンばかりやっているODの子もいれば、そうでない子もいます。
ゲームやスマートフォンの使用を制限すればODがよくなる、という単純な問題ではありません。
ゲームやスマートフォンの連続使用に、下記のようなODの悪化要因が重なればODは悪化します。
① 水分摂取不足
② 日常活動性の低下(寝そべったり座ったりする時間が長くなる)
③ 不規則な睡眠リズム
④ 精神的ストレス
⑤ 服薬忘れ
逆に言えば、上記5つが生じないようにすれば、ゲームやスマートフォンを連続的に使用していたとしても、ODに悪影響はないということになります。
朝起きることができず、不登校になっています。医療機関を受診させたいのですが、子供が嫌がっています。無理矢理にでも連れていくべきでしょうか?
子供が受診を拒むケースは主に2つです。
1つは、子供も自身が自分は病気ではないと思っているケースです。
つまり、朝起きられなかったり、学校に行けなかったりする理由が他にある、と子供自身が考えているケースです。
例えば、友人関係でトラブルがあるにもかかわらず、誰にも話せず黙っていることもあります。
このような場合は学年が変わったり、進学したりすることでOD症状が消失しますので、嫌がる子供を無理矢理受診させる必要はありません。
もう1つは、子供が保護者に反抗して受診を拒否するケースです。
このような場合、無理矢理受診させて、仮にODの診断に至ったとしても、子供が治療に積極的になるとは考えられません。
一度壊れた親子関係を修復するのは非常に大変です。また、親への拒否感から部屋に閉じこもり、活動量が低下することでかえってODが悪化する事態となってしまします。
子供が医療機関への受診を納得するまで、やさしく説明し、ゆっくり待つことも大切です。