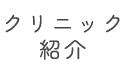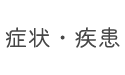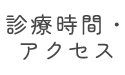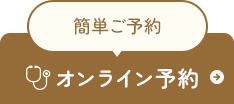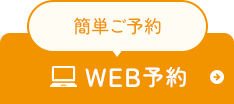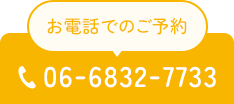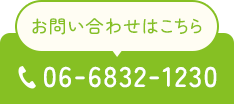RSウイルスの症状とは?ピークから、治療法まで詳しく解説
RSウイルス感染症は、乳児から高齢者まで何度でもかかる可能性がある呼吸器感染症です。特に乳幼児では重症化するリスクが高く、注意が必要です。このページでは、RSウイルス感染症の主な症状や経過のピーク、検査の対象や方法、治療の流れ、家庭でできる対策、そして重症化を防ぐための予防策まで、年齢別にわかりやすく解説します。
- 大人も子供もかかる「RSウイルス感染症」とは
- RSウイルス感染症の症状
- RSウイルス感染症の症状のピークは?
- RSウイルス感染症の原因となる感染経路
- RSウイルス感染症の検査方法
- RSウイルス感染症の治療方法
- RSウイルスの重症化を予防する注射製剤について
大人も子供もかかる「RSウイルス感染症」とは
 RSウイルスは、乳幼児の気道感染症において重要視されているウイルスで、呼吸器系に感染します。母親からの移行抗体が存在するにもかかわらず、生後数週から生後6か月の期間に最も重症な症状を引き起こします。その名前は「Respiratory」を略したもので、「呼吸に関連する」という意味があります。
RSウイルスは、乳幼児の気道感染症において重要視されているウイルスで、呼吸器系に感染します。母親からの移行抗体が存在するにもかかわらず、生後数週から生後6か月の期間に最も重症な症状を引き起こします。その名前は「Respiratory」を略したもので、「呼吸に関連する」という意味があります。
このウイルスは感染力が強く、ほとんどの子供が2歳までに感染するとされています。かかっても免疫が完全には形成されないため、複数回感染することがあります。潜伏期間は2日~8日で、症状が出る前や消えた後も数週間は他者に感染させる可能性があります。
RSウイルス感染症の症状
RSウイルス感染症は、子供の年齢や個々の状態によって、症状の持続期間や重さが異なります。一般的に以下のような症状が見られます。
- 鼻水
- 咳嗽
- 喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューといった音を伴う呼吸)
- 呼吸困難(咳や喘鳴で眠れなくなる)
- 発熱(多くは37~38℃程度)
年長の子供や学童では、軽い鼻水や咳の症状が徐々に改善されるケースがほとんどです。しかし、赤ちゃんや乳幼児に感染すると、最初は軽い鼻水から始まりますが、時間が経つにつれて喘鳴や呼吸困難の症状が現れ、細気管支炎や肺炎に至ることも多いため注意深く経過を観察する必要があります。また、中耳炎などの合併症を引き起こすこともあります。
乳幼児は重症化しやすい?
 RSウイルスは、軽度の風邪のような症状で済むこともあれば、細気管支炎や肺炎のような重症状態に至り、入院治療が必要になるケースもあります。大人の場合は通常、風邪の症状で済むことが多いですが、新生児や乳幼児は重症化しやすいとされています。実際、乳幼児の肺炎の約50%がRSウイルスによるものであり、細気管支炎の原因の50~90%もRSウイルスによるものと言われています。 潜伏期間は2~8日間で、多くは4~6日間とされています。発熱、鼻水、軽い咳などの症状は2~3日続くことが一般的です。完治までには通常7~12日かかります。
RSウイルスは、軽度の風邪のような症状で済むこともあれば、細気管支炎や肺炎のような重症状態に至り、入院治療が必要になるケースもあります。大人の場合は通常、風邪の症状で済むことが多いですが、新生児や乳幼児は重症化しやすいとされています。実際、乳幼児の肺炎の約50%がRSウイルスによるものであり、細気管支炎の原因の50~90%もRSウイルスによるものと言われています。 潜伏期間は2~8日間で、多くは4~6日間とされています。発熱、鼻水、軽い咳などの症状は2~3日続くことが一般的です。完治までには通常7~12日かかります。
症状が悪化すると、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューといった呼吸音)、喉元や鎖骨の上、肋骨の下が凹む陥没呼吸、呼吸困難によるチアノーゼ(鼻や唇が青黒くなる)が見られることがあります。生後1か月未満の新生児では、軽症であっても突然の無呼吸発作を起こすことがあり、乳幼児突然死症候群の原因の一つと考えられています。また無呼吸は早産児や低出生体重児に多いとされています。
残念なことに、RSウイルスに対する特効薬は未だに存在せず、治療は主に症状を和らげるための酸素投与、輸液、呼吸管理などです。重症化リスクが高い乳幼児には、医師の判断に応じて重症化を予防する薬が使用されることがあります。 また、母子免疫を獲得するための乳幼児向けワクチンと、60歳以上の高齢者向けワクチンが開発中であり、将来的には市場に出回る予定です。
RSウイルス感染症の症状のピークは?
症状のピークは発症後4~5日目
RSウイルス感染の症状は通常、発症後4~5日目に最も強くなります。咳、鼻水、発熱などの症状は、1週間程度で落ち着き、回復に向かうことが多いです。
症状が最も強い時期には、鼻水や咳のために母乳やミルクを飲むのが難しくなることもあるため、少量を頻回に飲ませる、部屋の湿度を保つなどの対策が効果的です。特に咳がひどくて眠れない場合は、上半身を高くして横になると楽になることがあります。
布団の下にバスタオルを敷いて傾斜をつける、抱っこするなどして快適な姿勢を取らせてあげると良いでしょう。
RSウイルスは自然に治ることが多いので、お子様の様子が良く、呼吸に苦しみがなければ、焦らず様子を見るか、医師に相談してください。しかし、発症から4~5日が経過しても症状が改善しない、または苦しそうな呼吸をしている、食事や水分を摂取できないなど、症状が悪化している場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
RSウイルス感染症の原因となる感染経路
 RSウイルス感染症の感染経路は下記の通りです。
RSウイルス感染症の感染経路は下記の通りです。
飛沫感染
くしゃみや咳から放出されるウイルスを吸い込むことで起こる感染です。予防にはマスク着用が有効です。
接触感染
ウイルスが付着した鼻汁やよだれ、または衣類やドアノブなどについた飛沫に触れた後、口や鼻を触ることで感染します。予防には流水石鹸での手洗いを含めた手指衛生が重要です。
RSウイルス感染症の検査方法
迅速検査
 鼻の奥を綿棒でこすって検体を取り、ウイルス抗原を検出する方法です。迅速に診断を行うことが目的でウイルス分離やPCR検査に比べると精度は劣ります。結果は約10分で判明しますが、RSウイルスに暴露される機会が増える年長児ではRSウイルスに対する中和抗体によってウイルス増殖に抑制がかかり、ウイルス排泄期間も短くなるため偽陰性が増えてしまいます。
鼻の奥を綿棒でこすって検体を取り、ウイルス抗原を検出する方法です。迅速に診断を行うことが目的でウイルス分離やPCR検査に比べると精度は劣ります。結果は約10分で判明しますが、RSウイルスに暴露される機会が増える年長児ではRSウイルスに対する中和抗体によってウイルス増殖に抑制がかかり、ウイルス排泄期間も短くなるため偽陰性が増えてしまいます。
1歳を過ぎると検査はしない?
RSウイルス感染の可能性が高い場合でも、必ずしも全ての子供が検査を受けるわけではありません。小児科でのRSウイルス検査は、主に1歳未満の乳児に限定されています。これは、特に生後6ヶ月までの乳児が重症化するリスクが高いため、感染の有無を確認し、その後の治療方針を迅速に決定する必要があるからです。
1歳を超えると、保険適応がありません。これは、重症化のリスクが減少し、RSウイルス感染症が特効薬を必要とせず自然治癒することが多いためです。しかし、1歳以上の子供であっても、基礎疾患がある場合や、生後6ヶ月未満の兄弟がいる場合など、検査が推奨される状況もあります。そのため、受診する際は、子供の健康状態や家族の状況を正確に伝えることが大切です。
RSウイルス感染症の治療方法
病院で行う治療法
RSウイルス感染症の治療は、発熱や呼吸器系の症状を軽減するための対症療法が中心です。鼻腔吸引(鼻吸い)なども有効です。現在、RSウイルスに特化した治療薬は存在しませんが、症状に応じて去痰剤や気管支拡張剤などの薬が処方されることがあります。また、細菌感染が併発していると疑われる場合には、抗菌薬(抗生剤)の使用も検討されます。
おうちでできる治療法
鼻腔吸引機(鼻吸い機)があるご家庭では、鼻腔吸引をおすすめしています。呼吸が楽になるだけでなく、中耳炎などのリスクを下げることができるため非常に有効です。鼻腔吸引は嫌がるお子さんも多く、泣いた後に結局また鼻水がでるのですが、泣いた後の鼻水はサラサラなことが多く、あまり問題になりません。RSウイルス感染のせいで増えたどろっとした鼻水を取ることが目的です。慣れてくればお子さん自身で鼻吸いをすることも可能なので、まだお持ちでないかたは購入をおすすめします。
赤ちゃんから大人まで、誰でも何度でも感染する可能性があるため、ご家族で手洗いやうがいを日常的に行い、いざ誰かが罹患した際はマスク着用を徹底するなど予防に努めることが大切です。
ご家庭でできる対策として、以下の方法もぜひ取り入れてみてください。
呼吸が楽になる環境づくり
加湿器を使用して湿度を適切に保ち、呼吸がしやすい環境を整えましょう。ただし、加湿器の手入れもしっかりお願いします。
こまめに水分補給
脱水を防ぐためにも、少量ずつで構わないのでこまめに水分を取らせることが大切です。
RSウイルスの重症化を予防する注射製剤について
重症化を防ぐ注射製剤(ワクチン)についての詳細は、以下のページでご紹介しています。