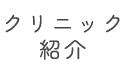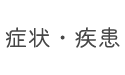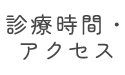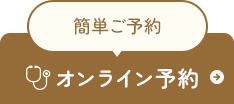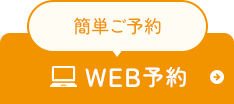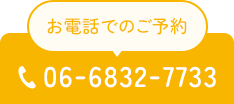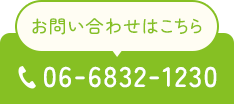溶連菌感染症に気づかず放置するとどうなる?うつるリスクや登校時の注意点
溶連菌感染症は、子供に多く見られる感染症ですが、大人や家族にもうつる可能性があります。
本記事では、溶連菌感染症の見逃しやすい症状、放置によるリスク、検査・治療法、再感染の予防法、登園・登校の目安までをわかりやすく解説します。
- 大人にもうつる「溶連菌感染症」
- 溶連菌感染症の見逃しやすい初期症状とは?
- 溶連菌感染症は病院へ行くべき?
- 溶連菌感染症はどうやってうつる?
- 溶連菌感染症の潜伏期間(登校・登園の目安)
- 溶連菌の検査方法
- 溶連菌感染症の治療方法
- 溶連菌感染症に気づかず放置してしまうとどうなる?
大人にもうつる「溶連菌感染症」
 溶連菌感染症は、A群β溶血性レンサ球菌によって引き起こされる感染症です。最も頻度が高いのは喉の痛みや発熱を伴う咽頭炎(いんとうえん)で、他にも皮膚の感染症(とびひや蜂窩織炎)、丹毒(たんどく)、猩紅熱(しょうこうねつ)、首の深いところの感染症(扁桃周囲膿瘍や咽後膿瘍)、壊死性筋膜炎などが知られています。
溶連菌感染症は、A群β溶血性レンサ球菌によって引き起こされる感染症です。最も頻度が高いのは喉の痛みや発熱を伴う咽頭炎(いんとうえん)で、他にも皮膚の感染症(とびひや蜂窩織炎)、丹毒(たんどく)、猩紅熱(しょうこうねつ)、首の深いところの感染症(扁桃周囲膿瘍や咽後膿瘍)、壊死性筋膜炎などが知られています。
子供に多いが、大人も注意が必要な「咽頭炎」
ここでは咽頭炎について触れていきます。溶連菌による咽頭炎は、子供の集団生活の場(学校や幼稚園など)を通じて広がりやすい感染症ですが、3歳未満での罹患は少ないとされています。症状には喉の痛み・嚥下痛、発熱、首の前のリンパ節の腫脹と圧痛があり、時に腹痛、嘔気、発疹、イチゴ舌を伴います。複数回感染することも少なくありませんし、家族内感染もよくあるため、感染した子供がいる家庭ではマスクの使用や手洗い・うがいの徹底が重要です。
溶連菌感染症の見逃しやすい初期症状とは?
 幼児~学童期の子供の場合、2~5日程度の潜伏期間を経た後に、喉の痛みや発熱、頭痛、倦怠感、食欲不振、腹痛など風邪に似た初期症状が起こります。
幼児~学童期の子供の場合、2~5日程度の潜伏期間を経た後に、喉の痛みや発熱、頭痛、倦怠感、食欲不振、腹痛など風邪に似た初期症状が起こります。
中でも特に目立つ症状は、喉の痛みです。咽頭粘膜の赤みや上あごの点状出血、イチゴ舌(舌の表面にイチゴのようなブツブツができる)が特徴的な所見です。扁桃腺(口蓋扁桃)に白い膿(滲出物)を認めることもありますが、頻度は25%と高くありません。一方で似た症状を示すアデノウイルス扁桃炎では白い膿(滲出物)が目立つ割に喉の痛みが目立たないことが多いと言われています。
発疹を伴うケース
発熱や喉の痛みが出てから1~2日経過した後には、体にかゆみを伴う発疹が現れることもあります。抗菌薬(抗生剤)治療により、これらの症状は通常1~2日で改善しますが、皮膚落屑(皮膚の表面が剥がれ落ちる症状)が見られたり、苺舌が数週間出続けたりすることがあります。
3歳未満の乳幼児の場合は目立った症状が起こらず、ぐったりしている、発熱、咳、鼻水、哺乳不足などの非典型的な症状が見られます。
溶連菌感染症は病院へ行くべき?
溶連菌感染は自然に治ることもあり、病院への受診が常に必要とは限りませんが、合併症を避け、症状を軽減するためには早期の医療相談が推奨されます。
以下のような症状がある場合は、脱水や他の合併症の兆候である可能性が高いため、速やかに医療機関を受診することが重要です。
- 喉の痛みが激しく、唾液や水分を飲み込むことができない
- 高熱が4日以上持続している
- 泣いても涙が出ない、尿量が減少している
- 口や唇が乾燥している
- 元気がなく、ぐったりした様子を見せている
- 呼びかけに反応しない、視線が合わない
- 呼吸が速い、息苦しそうにしている
- 痙攣が発生している
- 嘔吐が頻繁に起こる
溶連菌感染症はどうやってうつる?
溶連菌感染症は感染力が強く、人から人へと簡単にうつすリスクがあります。ここでは、感染経路についてご紹介いたします。
接触感染
感染者の皮膚や共有される物品(例えば手洗い場のタオル)、おもちゃなどについた病原体を吸い込むことで感染します。
飛沫感染
感染者の咳やくしゃみによって放出される病原体を吸い込むことで感染します。
溶連菌感染症は、家族間での感染が起こりやすいため、手洗い、うがいなどの予防策が有効です。この病気は特に、保育園や学校に通う子供達に多く見られますが、大人も家庭内で感染することがあります。治癒後も再感染の可能性があるため、地域の感染状況に注意し、日常的な予防措置を継続しましょう。
溶連菌感染症の潜伏期間や登校・登園の目安
溶連菌感染症の潜伏期間は通常2〜5日です。抗菌薬(抗生剤)の治療開始後24時間以上経過し、全身状態が良ければ登園・登校が可能です。喉に強い痛みを伴ったり、高熱、頭痛、吐き気、腹痛、発疹などの重い症状が続く、長引いたりする場合は無理をせず、医師の診察を受けるようにしましょう。
溶連菌の検査方法
 子供が溶連菌感染症にかかっているかどうかは、症状やその時の感染症の流行によって推測されることがありますが、感染が疑われる場合は、以下の3つの検査を通じて診断が行われます。
子供が溶連菌感染症にかかっているかどうかは、症状やその時の感染症の流行によって推測されることがありますが、感染が疑われる場合は、以下の3つの検査を通じて診断が行われます。
迅速抗原検査
迅速抗原検査キットを使用すると、喉の奥から綿棒で採取したサンプルに溶連菌が存在するかどうかを検査できます。このキットは溶連菌が存在する場合に約80%の確率で陽性反応を示します。完全ではないものの、結果が約5分で得られるため、医療現場で広く利用されています。
血液検査
血液検査を通じて、溶連菌に対する抗体のレベルを測定します。感染から数週間後に抗体が生成され始め、1ヵ月後にはピークを迎えるため、この検査は感染初期の診断には適しません。この検査は主に感染後の合併症を確認する際に使用されます。
培養検査
培養検査は、喉の粘膜から採取したサンプルを培養し、溶連菌を含めた細菌の存在を確認する方法です。この検査は迅速抗原検査キットに比べて精度が高く、より信頼性のある結果を提供しますが、結果が得られるまでには数日から1週間程度要します。
溶連菌感染症の治療方法
 溶連菌感染症の治療には抗菌薬(抗生剤)が用いられます。特に、ペニシリン系の薬剤が有効です。
溶連菌感染症の治療には抗菌薬(抗生剤)が用いられます。特に、ペニシリン系の薬剤が有効です。
注意が必要な抗菌薬と副作用
ピボキシル基を有する抗菌薬(フロモックス®、メイアクト®、トミロン®、オラペネム®)は短期間の投与であっても乳幼児に低血糖や痙攣を起こしてしまう(二次性カルニチン欠乏から)可能性があるため、不必要な処方は慎むべきとされています。
抗菌薬による副作用にもご注意ください
抗生物質の服用により腸内フローラが乱れ、下痢を引き起こすことがあるため、副作用が心配な場合は医師に相談し整腸剤の処方を検討してください。抗生物質を服用すると、溶連菌は治療開始後約24時間で大幅に減少(除菌率は80~90%と言われています。)しますが、再発防止と合併症予防のためには10日間しっかり飲み切ることが望ましいです。特定の抗菌薬(抗生剤)に対してアレルギーのある方は、別のアレルギー反応を起こさない(であろう)抗菌薬(抗生剤)に変更させていただきますので、ご相談ください。
また、発熱は免疫反応の一部ですので、体力に問題がなければ(食べる、飲む、寝るができれば)解熱剤を使わずに様子をみることが推奨されます。回復を促すためには、十分な水分補給と安静に努めることが大切です。
溶連菌感染症に気づかず放置するとどうなる?
溶連菌感染症を放置すると、以下のような深刻な合併症を引き起こす可能性があります。
お早めに医療機関を受診しましょう。
溶連菌感染症の合併症
リウマチ熱
溶連菌による咽頭炎の合併症として発生する急性の非化膿性炎症であり、心臓、関節、神経系、および皮膚に影響を与えることがあります。リウマチ熱は心臓の弁に損傷を与え、長期的には心臓病を引き起こす可能性があります。
急性糸球体腎炎
溶連菌による咽頭炎の約1~3週間後に腎臓の小さなフィルターである糸球体が炎症を起こし、血尿や蛋白尿、浮腫、高血圧などの症状が現れます。女児よりも男児に多いとされています。
蜂巣炎や丹毒
溶連菌が皮膚の浅い層や深い皮下組織に感染し、皮膚が赤く腫れ、痛みを伴います。蜂巣炎の一種である丹毒は溶連菌が皮膚の浅い層に感染しておこる病気で、境界明瞭なやや隆起した赤い発疹(紅斑)が顔や四肢に多くみられます。重症化すると敗血症を引き起こすことがあります。
猩紅熱
溶連菌による咽頭炎の特殊型で、紙やすり様のざらついた手触りの皮疹や紅斑が特徴的で、後に落屑(らくせつ)と呼ばれる皮膚の角質の脱落を伴うこともあります。